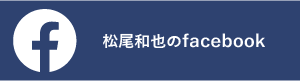日本、ドイツ、スイスの省エネ基準を比較してみた④
日本の基準が必要とする「暖房負荷」を考える
次に暖房用一次エネルギーから日本の基準が必要とする「暖房負荷」をどの程度に考えているのかを逆算した。ドイツ、スイスに関しては最初から負荷に関する暖房負荷の基準が出ているのでそのまま使っている。なお、暖房負荷とは「一定温度に室温を保った際に暖房期間を通算してどれだけの熱量が必要かを合計したもの」と考えていただければわかりやすいかと思う。暖房負荷は主に「断熱性」「気密性」「日射取得」で決まるので、暖房器具になにを使うのか?PEFの値がいくらなのかといったことはまったく関係ない。
下図Aにて各国が考える冷暖房負荷を比較してみる。これを見て分かるのは暖房負荷単体でみると、一次エネルギーの比較以上に差が大きいことだ。トップランナー基準の外皮性能をもってしてもパッシブハウス基準からすると4倍悪く、改正省エネ基準だと6倍も悪いということがわかる。これはすなわち、同じ温度を維持するのに4倍もしくは6倍のエネルギーを必要とすることにほかならない。実際に日本の住宅メーカーも含めて暖房負荷を表示している「建もの省エネ健康マップ」を見てもほとんどの大手メーカーは暖房負荷が80~95kwh/m2に納まっていることが読み取とれる(http://tatemono-nenpi.com/map/)。
下図Bでは、6地域以外の地域の冷暖房負荷も比較してみた。これを見ると北海道の中でも1地域においては16倍もの違いが出ている。1地域はドイツの最寒い地域よりも寒いと思われる。よってこのような値が出ると思われる。例えば旭川の1月の平均気温は-7.5℃だが、ドイツ最北部のハンブルクでは1.5℃くらいである。日射量が違うので同じ土俵での比較ではないが、1.5℃というのは福島に該当する。福島は4地域に該当するので1月の外気温が同等の地域で比較すると実に11倍もの差があることがわかる。
ここでもうひとつ制度を作っている人及び大半の実務者、施主が考えている「部分間欠冷暖房」の基準値も比較してみる(下図C)。
これを見ると意外なことが見える。温暖地ほど部分間欠暖房にすると確かにエネルギー量が明らかに小さくなることがわかる。しかし、寒冷地になるほど差が非常に小さくなっている。これも寒冷地では全館暖房が当たり前になる理由のひとつなのかもしれない。
しかし、ここで注意しておく必要がある。部分間欠暖房をもってしてもすべての地域でドイツとスイスが全館暖房したときの基準値を大幅に上回っている。これが意味することは「日本人が寒さを我慢し、健康を犠牲にして生活しても、全館ぽかぽかで暖かいドイツやスイスの住宅よりもたくさんのエネルギーを使ってしまう」ことを表している。また、改正省エネ基準(次世代省エネレベル)が想定している自然温度差(無暖房時の室温)はせいぜい7℃程度である。東京や大阪でも1月の最も寒い日の早朝は0℃くらいになる。ということはこういう日の朝は室温が10℃を切っている可能性が十分にあることを意味する。
わたしがここで言いたいのは、「だから日本の基準が悪い」ということではない。ドイツやスイスは「人間が健康で快適に過ごしていく上で室温20℃というのは死守しなければならない。しかしながら、CO2削減も絶対に必要である。エネルギー価格は確実に上昇傾向にある。これらの相反する条件を満たすべく目標から逆算すると暖房負荷を極力小さくするしかない」と考えている、ということである。